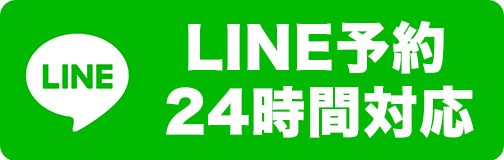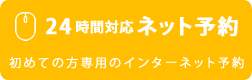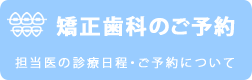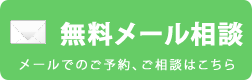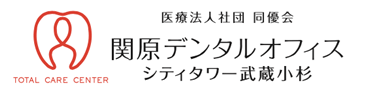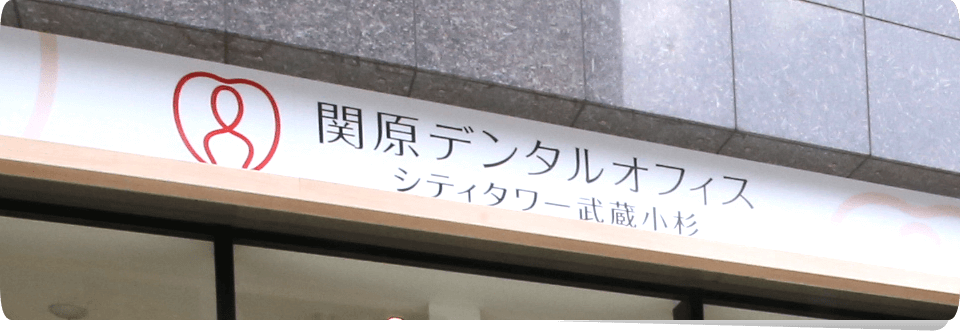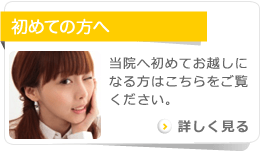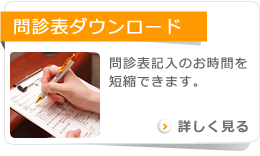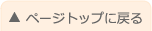こんにちは。
関原デンタルオフィスです。
年の初めを迎えると、「今年こそ健康に気をつけよう」「生活習慣を見直そう」と考える方も多いのではないでしょうか。食事や運動、睡眠と同じように、実はお口の健康も一年のスタートに見直しておきたい大切なポイントです。むし歯は一度できてしまうと自然に治ることはなく、進行すれば治療が必要になります。だからこそ、日々の予防が非常に重要です。今回は、新年に改めて確認しておきたいむし歯予防の基本についてご紹介します。
むし歯の原因を知ることが予防の第一歩
むし歯は、単に甘いものを食べたからできるわけではありません。お口の中にいるむし歯菌が、糖分をエサにして酸を作り、その酸によって歯が溶かされることで発生します。この「歯が溶ける状態」が長く続くほど、むし歯は進行していきます。歯の質、細菌の量、糖分の摂取、そして時間、この4つの要素が重なったときに、むし歯はできやすくなります。つまり、どれか一つだけに気をつけるのではなく、複数の要素をバランスよく管理することが予防には欠かせないのです。
新年に見直したい、むし歯予防の基本習慣
まず確認したいのが、毎日の歯磨きが本当に「正しく」できているかどうかです。磨いているつもりでも、歯と歯の間や歯ぐきのきわには磨き残しが多く、そこに汚れがたまりやすくなります。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、むし歯のリスクは大きく下げることができます。
次に意識したいのが、糖分との付き合い方、いわゆるシュガーコントロールです。むし歯予防では甘いものを「どれだけ食べたか」よりも、「どのように、どれくらいの頻度で摂取しているか」が重要になります。間食の回数が多かったり、甘い飲み物を長時間かけて飲んだりすると、お口の中が酸性に傾く時間が長くなり、歯が溶けやすい状態が続いてしまいます。この状態を時間の経過とともに示したものが「ステファンカーブ」であり、だらだら食べや飲みを続けることが、むし歯を招きやすい環境を作る理由が分かります。
さらに、むし歯予防に欠かせないのがフッ素の活用です。フッ素には歯の質を強くし、酸によって溶けかけた歯を修復する働きがあります。年齢に関係なく、フッ素入り歯磨き粉を毎日のケアに取り入れることで、むし歯に負けにくい歯を育てることができます。
プロの目で守るむし歯予防
セルフケアをどれだけ丁寧に行っていても、磨き癖や見えない部分の汚れはどうしても残ってしまいます。定期検診では、むし歯の早期発見だけでなく、歯石やプラークの除去、歯磨き方法の見直しなど、予防を目的とした専門的なケアを受けることができます。初期のむし歯であれば、削らずに経過観察が可能な場合もあり、定期的にチェックすることで歯を守る選択肢が広がります。
また、生活習慣や食事内容、年齢によるリスクの変化に応じて、個々に合った予防方法を提案できるのも歯科医院ならではの強みです。むし歯は「治す」よりも「防ぐ」ほうが歯への負担も少なく、結果的に時間や費用の面でもメリットが大きくなります。
まとめ
むし歯予防は、特別なことをするよりも、毎日の基本を丁寧に続けることが何より大切です。正しい歯磨き、糖分との付き合い方、フッ素の活用、そして定期検診、この積み重ねが将来の歯の健康を守ります。新しい一年の始まりにお口のケアを見直すことは、これからの生活をより快適にする第一歩です。今年もむし歯のない健やかな毎日を目指して、できることから始めていきましょう。